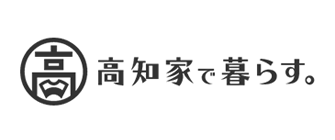本文
障害福祉サービス・障害児通所支援
本ページでは、香美市が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)及び児童福祉法に基づく、「自立支援給付」と「障害児通所支援」についてご紹介致しております。
概要
障害者総合支援法に基づくサービスは、個々の障害のある人々の障害程度や検討すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
地域生活支援事業は、都道府県が実施する事業と市町村が実施する事業があります。
児童福祉法に基づく支援は、「障害児通所支援」と「障害児入所支援」に大別され、「障害児通所支援」は市町村が、「障害児入所支援」は都道府県により実施されます。
障害福祉サービス等を利用される方は、市町村に申請のうえ、支給決定の後にサービス等提供事業者と契約し、サービス等を利用します。
障害福祉サービス等の利用にあたっては、自己負担(利用額(事業所の報酬額)の1割)と実費負担(食費、家賃等)が必要となります。ただし、自己負担については、収入に応じて月額上限負担額が設定されており、また、そのほかにも様々な軽減措置が設けられています。
対象となる障害者
身体障害者
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
知的障害者
知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者
精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法にいう発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者
難病等対象者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者のうち、18歳以上である者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものについては、こちらをご覧ください。
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省)
障害児
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
注意事項
実際に障害福祉サービス等を利用するにあたっては、サービス毎に条件が設定されているため、上記の条件に該当する方であっても、サービスを利用できないことがあります。
障害福祉サービスの内容と利用対象者
障害者福祉サービスの内容及び利用対象条件については、こちらをご覧ください。
障害福祉サービスについて(厚生労働省)
障害児通所支援
児童福祉法に基づく、障害児通所支援には、下表のようなものがあります。
主に就学の前後で利用できる支援が変更となります。
| 種類 | 支援内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
| 医療型児童発達支援 | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて、治療を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
障害児通所支援の利用を検討されている方は、こちらをご覧ください。制度内容や手続きの流れ、香美市内の事業所の情報を掲載しています。
障害児通所支援 利用の手引き [PDFファイル/1.35MB]
このほかにも、一定の条件を満たす障害児については、障害福祉サービスのうち「居宅介護」、「行動援護」、「同行援護」、「重度障害者等包括支援」、「短期入所」の利用が可能です。
なお、障害児入所支援は、都道府県事業となりますので、高知県地域福祉部障害福祉課(障害児支援担当 088-823-9663)へお問い合わせください。
利用者の負担
サービス等の利用にあたっては、自己負担(利用額(事業所の報酬額)の1割)と実費負担(食費、家賃等)が必要となります。ただし、自己負担については、世帯の収入に応じて月額上限負担額が設定されており、また、そのほかにも様々な軽減措置が設けられています。
障害者の利用負担
障害者福祉サービスの利用に係る自己負担は、世帯の収入に応じて、次のような月額上限負担額が設定されています。
また、このほかにサービスによっては、実費負担(食費、家賃等)が必要となるものがあります。
月額上限負担額
| 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※20歳以上の施設入所者及びグループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く |
9,300円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)で、20歳以上の施設入所者 | 37,200円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)で、グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者 | |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) |
ここでの世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、障害者本人及びその配偶者のみとなります。ただし、20歳未満の施設入所者については、障害児同様に保護者の属する世帯となります。
市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯
市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。
施設入所者とは、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設又は指定障害児入所施設等に入所又は入院している者を指します。
障害児の利用負担
障害児通所支援の利用に係る自己負担は、世帯の収入に応じて、次のような月額上限負担額が設定されています。
また、このほかにサービスによっては、実費負担(食費)が必要となるものがあります。
月額上限負担額
| 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
ここでの世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、保護者の属する世帯となります。
市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯
市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。
就学前の障害児の発達支援の無償化(令和元年10月1日から)
「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」は、障害児通所支援に係る自己負担については、世帯の収入状況に係らず0円となります。ただし、実費負担(食費)は必要となります。
そのほかの軽減措置
そのほか種々の軽減措置については、こちらをご覧ください。
障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き【令和6年4月版】 [PDFファイル/3.4MB]
(出典:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部)
申請手続き
申請からサービス利用までの流れ
- 申請
障害者手帳のほか必要な書類をご用意いただくこととなります。詳しくは、下記「申請に必要なもの」をご確認ください。 - 障害支援区分の判定
障害支援区分の必要な障害福祉サービスを利用される方のみ必要となります。
障害支援区分の必要な障害福祉サービスかどうかの確認は、厚生労働省のホームページ「障害福祉サービスについて」でご確認ください。 - 指定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)との契約
- サービス等利用計画案の提出
- 支給決定・受給者証の交付
- 障害者福祉サービス提供事業者との契約
利用までに要する期間
新規申請の場合、障害福祉サービス等の利用までには、申請から1ヶ月から2ヶ月程度を要します。特に、障害支援区分の認定が必要なサービスを利用される場合は、支給決定までに2ヶ月程度の期間が必要です。
また、支給決定を受けた場合でも、利用したいサービス提供事業者の空き状況によっては、支給決定後直ぐには利用できないことがあります。
転入予定者
香美市へ転入を予定されている方で、転入前にお住いの市町村で障害福祉サービスの支給決定を受けており、転入日から利用している障害福祉サービス等を利用されたい場合は、転入される1月以上前に下記の手続きを完了するようにしてください。
- 転出元市町村(現在お住いの市町村)へ香美市に転出すること及び香美市からの資料請求に対応いただきたいことを申し出る。
円滑な支給決定のため、2の申請後に既支給決定に係る認定調査票、概況調査票等の情報提供を香美市から転出元市町村に依頼します。 - 香美市への申請(郵送可)
- 香美市へ転入後に利用される相談支援事業所との契約
相談支援事業所を変更しない場合は、契約の必要はありません。 - 利用事業所との契約等
事業所を変更しない場合は、契約の必要はありません。
注意事項
支給決定には、1月程度の期間を要します。転入直前での申請となった場合は、香美市での支給決定が完了するまで障害福祉サービス等が利用できないこともありますので、ご注意ください。
初回更新時に訪問等により調査を行うことがあります。
そのほか
上記「利用者の負担」にありますとおり、支給決定にあたっては、世帯の収入状況を把握する必要があることから、対象の世帯員全員の確定申告(又は市町村申告)を実施いただく必要があります。全く収入がない場合であっても申告は必要となります。申告については、香美市税務収納課市民税班へお問い合わせください。
障害支援区分の認定を受けられる場合は、医師意見書が必要となることから、申請後に主治医の診断を受けていただく必要があります。
申請手続きは、利用開始時だけでなく、毎年の収入認定に係る申請及びサービス毎に決定された支給決定期間満了時の継続申請(原則、1年毎又は3年毎)が必要となります。
申請に必要なもの
上記「対象となる障害者」にある障害者等に該当することを確認するために障害等の内容により、申請時に以下の書類を提示又は提出いただくこととなります。
障害福祉サービス等の利用対象者であることを確認する書類
身体障害者
身体障害者手帳
知的障害者
療育手帳
意見書
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳
精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
医師の診断書(国際疾病分類Icd-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)
難病等の方々
医師の診断書
特定医療費(指定難病)受給者証
指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
障害児
障害者手帳
特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
通所支援サービス意見書
補足給付、特定障害者特別給付費等の給付に必要な書類
施設入所支援又は療養介護を利用されたい方
申請者及びその配偶者の前年中(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前々年中)の収入状況を把握する必要があることから、以下の書類等の提示、提出が必要となります。
障害年金等の受領金額がわかる書類(振替先預金口座の通帳)
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当の受領金額がわかる書類
仕送り収入、不動産等による家賃収入がある場合は、それらの受領金額がわかるもの(通帳等)
保険料、各種税金の領収証
各種加算などに必要な書類
次に示す加算や給付を受けるためには、各種書類の提出が必要となります。
共同生活援助に係る家賃補助 : 家賃証明書
地域生活移行個別支援加算 : 在所証明書等
社会生活支援特別加算 : 在所証明書等
精神障害者地域移行特別加算 : 退院証明書等
精神障害者退院支援施設加算 : 退院証明書等
申請書
障害者福祉サービス・障害児通所支援
| 申請内容 | 申請書 | 摘要 |
|---|---|---|
| 新規利用申請時 | 様式第1号 (サービスによって様式第24号) |
上記「申請に必要なもの」に示す書類を併せてご提出ください。 |
| 新規サービス申請時 (新しいサービスを利用するとき) |
上記「補足給付、特定障害者特別給付費等の給付に必要な書類」にある補足給付等を新規に給付されたい場合は、該当する書類を併せてご提出ください。 サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案の提出も必要となりますので、提出にあたっては、予め契約している特定相談支援事業所へ相談のうえ、提出をお願いいたします。 |
|
| 利用中サービスの 支給量の変更時 |
様式第1号 | サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案の提出も必要となりますので、提出にあたっては、予め契約している特定相談支援事業所へ相談のうえ、提出をお願いいたします。 |
| 特定相談支援事業所の変更 | ||
| 住所・氏名を変更したとき | 様式第14号 | |
| 利用者負担上限額管理事業者の 設定・変更時 |
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 | |
| 自立訓練、就労移行支援、自立生活援助、地域移行支援の標準利用期間を超えてサービスを利用したいとき | 利用期間延長に係る評価結果報告書 | |
各種申請書
いずれの申請書も印刷は、両面印刷でお願いします。
様式第1号 支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書 [Wordファイル/42KB]
様式第14号 申請内容変更届出書 [Wordファイル/35KB]
様式第24号 世帯状況・収入等申告書 [Wordファイル/26KB]
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [Excelファイル/17KB]
利用期間延長に係る評価結果報告書 [Excelファイル/16KB]
契約内容報告書(障害福祉サービス) [Excelファイル/18KB]
契約内容報告書(障害児通所サービス) [Excelファイル/25KB]
記載方法
様式第1号(新規申請) 支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書 [PDFファイル/136KB]
様式第1号(変更申請) 支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書 [PDFファイル/151KB]
様式第24号 世帯状況・収入等申告書 [PDFファイル/74KB]
障害者福祉サービス提供事業者・指定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)
香美市内にある障害福祉サービスの就労系事業所については、こちらのパンフレットをご覧ください。
香美市内の就労系事業所パンフレット [PDFファイル/8.3MB]
高知県内にある障害者福祉サービス提供事業者等については、こちらでご確認ください。
指定障害福祉サービス事業者等の公示(高知県障害福祉課)
お住いの市町村以外の事業所であっても、利用は可能です。
ただし、利用対象となる事業所であっても、定員に達しているなどの理由から直ぐに利用できないことや利用できる曜日、時間帯が制限されることがあります。また、多くの事業において、利用契約に先だって、障害内容等の確認や見学等が必要となっています。
地域生活支援事業
香美市においては、ここに示した自立支援給付以外にも、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく、地域生活支援事業を実施しております。
詳しくは、地域生活支援事業のページをご覧ください。