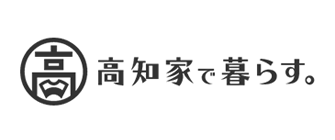本文
移動支援事業
外出困難な在宅の障害者等の生活行動範囲の拡大及び社会参加のため、外出時の移動を支援します。
香美市移動支援事業利用の手引き [PDFファイル/484KB]
対象者
香美市に在住しており(居住地特例により援護市町村が香美市である者を含む。)、以下の身体・知的・精神障害児・者又は難病等に罹患している次のような方が利用できます。
- 「移動」、「食事」、「排尿」、「排便」、「危険の認識」、「買い物」、「交通機関の利用」、「コミュニケーション」、「説明の理解」、「読み書き」といったことに支障のある障害者
- 「食事」、「排泄」、「移動」等に支障のある障害児の保護者
ただし、入所系の障害福祉又は介護保険サービスを利用されている方や代替できる障害福祉サービスを利用される方は、対象外となります。
詳しくは、利用の手引きをご確認ください。
身体障害者
身体障害者手帳の交付を受けている者
知的障害者
知的障害者手帳の交付を受けている者
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又は同等である者
難病等対象者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者のうち、18歳以上である者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものについては、こちらをご覧ください。
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省)
障害児
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
対象となる外出
利用できる外出は、以下の2つとなります。具体的な事例等を確認されたい場合は、利用の手引きをご確認ください。
社会生活上必要不可欠な外出
行政機関や金融機関での手続きや公共料金の支払、冠婚葬祭、日用品の買い物などが該当します。
社会生活又は余暇活動を充実させるための外出
散歩や娯楽施設への移動、趣味等のための外出同行などが該当します。
原則対象外となる外出
通勤、通学、通院及び営業活動等の経済活動にかかる外出
通年かつ長期にわたる外出、及び社会通念上適当でない外出
利用できる事業所
利用できる事業所は、香美市と委託契約をしている以下の事業所です。
障害の程度や内容により利用できない事業所もありますので、契約に当たっては、事業所と個別にご相談ください。
新規に事業所として登録(委託契約)を希望される場合は、こちらのページを確認ください。
| 事業所名 | 休所日 | 営業時間 | 対象者 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香美市社協 ヘルパーステーション八王子 |
土曜 |
8時30分から 17時15分まで |
身体障害者 知的障害者 精神障害者 |
香美市土佐山田町262番地1 | 0887-53-5800 |
| 富士屋ベターライフ香北 | 年末年始 | 8時30分から 17時30分まで |
身体障害者 知的障害者 精神障害者 |
香美市香北町美良布2673番地2号 | 0887-59-3113 |
|
ヘルパーステーションあさひ |
土曜 日曜 年末年始 |
8時30分から 17時30分まで |
特定なし | 香美市土佐山田町旭町4丁目2番6号 | 0887-57-6333 |
| ホームヘルパーステーション サステナ |
土曜 |
8時30分から 17時30分まで |
特定なし | 高知市本町3丁目6番37号 かわさき予備校ビル3階 | 088-873-3303 |
申請書
障害者福祉サービス又は障害児通所支援に係る支給決定を受けていない場合、上記「対象者」に該当するものであることを示す書類(手帳など)を併せてご提出ください。
| 申請内容 | 申請書 | 記載方法 |
|---|---|---|
| 新規に利用したいとき 継続に利用したいとき |
様式1 利用申請書 [Wordファイル/22KB] | 利用申請書 [PDFファイル/99KB] |
| 申請内容が変更となったとき 支給内容を変更したいとき |
様式3 変更申請書 [Wordファイル/22KB] |
障害者手帳以外に対象者であることを示す書類
精神障害者
精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
医師の診断書(国際疾病分類Icd-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)
難病等の方々
医師の診断書
特定医療費(指定難病)受給者証
指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
障害児
特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
利用者負担(令和3年4月以降)
利用者の利用料負担は、上限利用量の範囲内であれば、要した経費の1割となります。ただし、世帯の収入状況によって、標準利用量の範囲内であれば、下表に示す月額上限負担額が設けられています。
| 算定基礎単位 | 基準額 |
|---|---|
| 30分 | 1,400円 |
| 利用内容 | 標準利用量 | 上限利用量 |
|---|---|---|
| 基本部分 ・社会通念上必要不可欠な外出 ・社会生活又は余暇活動を充実させるための外出 |
30 時間/月 | 50 時間/月 |
| 特例部分 | 個別に利用決定にて定める | |
| 世帯の収入状況 | 利用者負担額 | 月額上限負担額 (障害者) |
月額上限負担額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
標準利用量を超過して利用した分は、 上限利用料を超過して利用した分は、 |
| 市町村民税課税世帯 (所得割額が16万円未満) |
経費の1割 | 9,300円 | 4,600円 | |
| 市町村民税課税世帯 (所得割額が28万円未満) |
経費の1割 | 37,200円 | 4,600円 | |
| そのほかの世帯 | 経費の1割 | 37,200円 | ||
※ 移動経費(有料道路通行料)、食事代、入場料等は利用者負担となります。
利用者が18歳以上の場合、世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、障害者本人及びその配偶者のみとなります。
市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯
市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。