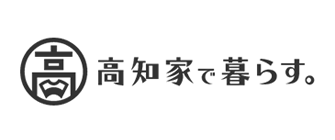本文
介護保険の利用
介護保険パンフレット
(クリックするとウェブブックでパンフレットをご覧になれます。)
サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳以上65歳未満で国民健康保険や職場の健康保険に加入している方(第2号被保険者)
※第2号被保険者のサービス利用は、老化に伴う疾病が原因で介護が必要になった方に限られます。
老化に伴う疾病とは [PDFファイル/73KB]
申請からサービス利用まで
サービスを利用するには、介護保険係への要支援・要介護認定申請が必要です。申請をすると、介護認定調査員による調査・介護認定審査会による審査を経て、必要な介護の度合い(介護度)が決まります。
1.申請
市役所の介護保険窓口へ要支援・要介護認定の申請をしましょう。申請は本人のほか、家族やケアマネージャー、介護保険施設などによる代行も可能です。
〇申請に必要な様式についてはこちらをご確認ください→介護保険に関する様式集
2.訪問調査・主治医の意見書
介護認定調査員がご自宅または施設を訪問して、本人や家族から心身の状態などを聞き取り調査します。また、市の依頼により主治医が意見書を作成します。
3.要介護認定
【一次判定】
訪問調査の結果と主治医の意見書の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
【二次判定】
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会を開き、どのくらいの支援や介護が必要か審査します。
4.認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に市から認定結果が通知されます。30日を超える場合は、申請者に対し介護認定延期のむねの通知をします。
5.ケアプランの作成
介護サービス計画はご自身で作成することもできますが、通常は居宅介護支援事業者に依頼します。(計画作成費用は自己負担がありませんので無料です。)
【要支援と認定された方】
市に設置されている地域包括支援センターに作成を依頼します。
【要介護と認定された方】
居宅介護支援事業所または介護保険施設に作成を依頼します。
ケアプランの作成は、
1.ケアマネージャー等が利用者の生活や心身状態等を把握し、課題を分析します。
2.目標を設定し、それを達成するための支援メニューを利用者・家族・サービス担当者で検討します。
3.利用するサービスの種類や回数を決定します。
6.サービスの利用
作成されたケアプランにもとづいてサービスを利用します。
利用料は、要介護度によって決められている利用限度額内であれば、かかった費用の1割、2割または3割が自己負担となります。
上限を超えてサービスを利用した場合、その超過した費用分は全額自己負担となります。
サービスの概要 [PDFファイル/97KB]
詳しいサービスの内容は、介護保険パンフレットの15ページから26ページでもご紹介しています。ご覧ください。
7.認定の更新
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新申請をする必要があります。
また、有効期間中に心身状態に変更があった場合は、認定の変更の申請が出来ます。
〇申請に必要な様式についてはこちらをご確認ください→介護保険に関する様式集