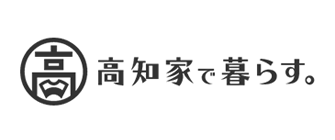本文
農業者年金
1971年に発足した農業者年金制度は,農業を取り巻く情勢の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の基本理念に即して、農業者の確保に役立てる制度として改正されました(2002年1月1日施行)。
新制度の特徴
積立方式で安心・安定
新しい農業者年金は、自ら積み立てた保険料とその運用実績によって受給額が決まる積立方式をとっています。従来型の賦課方式のように、加入者・受給者の数に左右されにくい、長期に安定した制度です。
| 積立方式 | 賦課方式 | |
| 保険料 | ・金利変動の影響を受けやすい ・受給者・加入者数の影響を受けにくい。 |
・年金受給者と現役加入者の比率により額が決まるため,人口構成の変動の影響を大きく受ける。 ・金利変動の影響は受けにくい。 |
| 経済変動への対応 | ・極度のインフレや賃金上昇があった場合には年金の実質的価値の維持は困難。 ただし、インフレに伴う金利上昇で運用益が増えれば年金額の増加につながる。 |
・極度のインフレ、賃金上昇があった場合でも、その時点での現役加入者の保険料負担により実質的価値を維持した年金支給が可能。 |
| 加入者保険料の使途 | 将来の自らの年金給付。 |
その時々での高齢世代の年金給付。 |
農業従事者だけが加入
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます(農地を持っていない農業者や配偶者・後継者も加入できます。旧制度の加入者で特例脱退した人でも、60歳未満であれば加入できます。
脱退は自由です。脱退一時金の支給はないものの、加入期間に関わらずそれまでに支払った保険料は将来の年金として受け取ることになります。
保険料の額は自分で決める!
保険料は月額2万円が基本ですが,6万7000円までの範囲で1000円単位で自由に決めることができ、額の見直しもいつでもできます。その時々の経済状況、また老後の将来設計により増減できるので便利です。もちろん、保険料月額が多いほど将来受け取る年金額も多くなります。
80歳まで保証された終身年金
当然,年金は終身受け取ることができますが、万が一、加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳になるまでに受け取るはずの年金(老齢年金)を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取ることができます。
早く加入するほど有利
農業者年金は複利方式です。加入期間が長いほど、運用益のアップが期待できます。
※ 複利方式…一定期間ごとに利息を元金に繰り入れ、それを次期の元金とする計算方法です。
担い手には保険料の国庫助成(政策支援)あり
認定農業者など、一定の要件を充たす農業者には保険料の国庫助成(政策支援)が、基本保険料2万円のうち最大半額、生涯で最大216万円の補助を受けることができます。この国庫補助額とその運用益は個人ごとに積み立てられ、将来受給する特例付加年金の原資になります。
※特例付加年金…受給には農地などの経営継承が必要になります。経営継承の時期について、年齢制限はありません。
保険料の助成対象者と助成額
| 区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
| 1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 6,000円(3割) |
| 5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者になることを約束した後継者 | 6,000円 | - |
税制面での大きなメリット!
保険料は全額(最高年額80万4000円)所得税の社会保険料控除の対象になります(個人年金の場合は控除額の上限は5万円)。所得が増えるほど節税効果があり、所得水準によっては政策支援より大きなメリットになる場合もあります。
また、預貯金は利子の20%が課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。受け取る年金についても公的年金等控除の対象になります。
☆加入の手続きは…
お近くのJAの窓口に備えつけてある加入申込書に所要事項を記入し、提出して下さい。