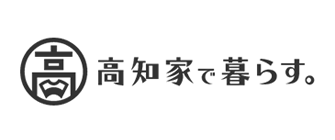本文
固定資産税についてのよくある質問
よくある質問
今年土地や家屋の売買をしたのですが、固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。年の途中で売買された場合でも、課税の納税義務者は変更しません。来年度から新所有者に課税させていただくことになります。
固定資産税の評価替えとは何ですか。
土地、家屋の固定資産税について、3年ごとに資産価格の変動等を考慮し「適正な時価」をもとに評価額を見直す制度です。評価替え:2024年(令和6年)度、2027(令和9年)度、2030(令和12年)度・・・
家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価額は、3年毎の評価替え年度に見直しを行います。そのため3年間価格は据え置かれます。評価額の計算方法は対象家屋と同一のものを評価替えの時点において建てるとした場合に必要とされる建築費に、建築後の年数から生じる損耗の状況(経年減点補正率)を乗じて求められます。物価が下落傾向にある時期は、比較的建築年の新しい家屋についても、評価替え毎に価格が下落しています。一方、建築費の上昇が続く時期は、評価額が据え置かれるので、評価替えの見直し年度でも評価額が下がらないことがあります。また、経過年数による減価補正率は下限が20%と決められており、20%に到達すると年数が経過しても減価されません。
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか。
土地の固定資産税評価額(以下、評価額)は、1994年(平成6年)度の評価替の際に地価公示価格の7割を目途にするとされました。しかし、この評価額を基に課税算定をすると、税額が大幅に上がるため、毎年当年度の評価額の一定割合に近づける負担調整措置が取られております。したがって、税額が上昇しているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
納税通知書に同じ地番の土地があります。どうしてですか。
原因としては主に、以下の2つが考えられます。
- 住宅用地の特例が適用されている場合
宅地は、小規模住宅用地、その他の住宅用地、非住宅用地の3種類に大きく分類されます。これらは、筆とは関係なく、土地の利用状況や面積に依存して区分され、納付書には別々に表記されます。 - 一筆の土地が複数の地目で課税されている場合
農地や山林の一部に家屋を建てた場合など、一筆の土地に複数の地目を認定することがあります。この場合、一筆の土地を地目ごとに課税上分けて計算します。
税額が急に上昇したが、どうしてですか。
原因としては主に以下の3つが考えられます。
- 住宅を取り壊しされた場合、住宅の建設されていた土地に対する住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。その結果、評価額は変化しないのに課税標準額が大きく上昇し、税額が大きく上昇します。
- 農地法第4条第1項、第5条第1項の規定により、宅地等への転用に係る許可を受けた後は、宅地等への転用が完了していない場合(農地のまま)でも、宅地等として評価、課税します。現況地目は宅地介在田又は、宅地介在畑となり外見上は農地のままですが、税額は大きく上昇する場合がほとんどです。
- 新築住宅に対する減額措置の期間が終了すると、税額があがります。新築住宅に対する減額措置とは、新築された住宅について、減額要件に適合すれば、一般の住宅は新築後3年分、3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分の固定資産税額(居住部分の床面積120平方メートルまで)の2分の1が減額される制度です。そのため期間が過ぎますと、減額措置がなくなるため、税額が上昇します。