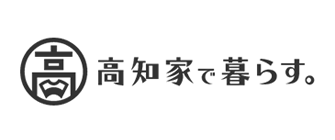本文
家屋にかかる固定資産税
家屋の評価
家屋の評価につきましては、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準として、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正(経年減点補正率)などを行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。
新・増築家屋の評価
新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・基礎・内外壁・柱・造作・天井・建具・床および建築設備などについての調査をします。
再建築費評点数の算出
再建築費評点数=標準評点数×各種補正係数×計算単位の数値(床面積または個数)
固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違い等による格差を補正して、部分別に単位当たりの評点数を求めます。次に、部分別毎の再建築評点数をすべて合計して再建築費評点数を算出します。
評価額の算出
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
評点1点当たりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)評価
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り評価額が3年間据え置かれ、3年毎の評価替えで見直しを行います。在来分家屋の評価額の計算につきましては、新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築評点数は、建築物価の変動分を考慮し、次のように計算されます。ただし、見直し後の評価額が建築物価の上昇率が大きく前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。
在来分家屋の再建築価格
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築評点数×建築物価の変動割合
評価額の算出
評価額=在来分家屋の再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
評点1点当たりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
2026年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額の2分の1が減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
※専用住宅=人が居住するためだけに使用する家屋
※併用住宅=一部を人が居住するために使用する家屋 - 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)については新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等については新築後5年度分
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
2026年3月31日までに新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅について、新築後一定期間の固定資産税額の2分の1が減額されます。
この減額を受けるには、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、税務収納課に申告する必要があります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)については新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等については新築後7年度分
住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置
1982年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する50万円を超える耐震改修工事をした場合、一定期間固定資産税の2分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります
減額対象となる改修工事の要件
- 1982年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であり、1戸当たりの改修工事費が50万円を超えること。
- 次のいずれかの者による証明を受けていること。
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・地方公共団体※)
※県の耐震改修補助事業を受けて耐震改修をしたものに限る。 - 2013年1月1日から2026年3月31日までの間に工事が完了していること。
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額対象になります。
減額される期間
| 改修工事完了年月日 | 減額期間 |
|---|---|
| 2013年1月1日から2026年3月31日 | 申告の翌年度から1年間 |
| ※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間 | |
申請に必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書(防災対策課発行)、または住宅性能評価書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(例→耐震改修工事費用の領収書の写し等)
申請書ダウンロード
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/53KB]
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(記入例) [PDFファイル/68KB]
バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置
2026年3月31日までに建物をバリアフリー改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。
減額対象となる改修工事の要件
新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること。
(貸家の用に供するものは除く)
次のいずれかの工事で、補助金等を除いた改修工事費の自己負担額が50万円を超えること。
- 通路・出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 床の段差解消
- 出入り口戸の改良
- 床の滑り止め化
次のいずれかの者が居住する住宅であること
- 65歳以上の者
- 要介護認定、又は要支援認定を受けている者
- 障害者
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。
減額される期間
バリアフリー工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間
申請に必要な書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)
- 工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
- 補助金・介護保険給付金等の決定通知書の写し
- 居住要件を確認できる書類(介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し等)
申請書ダウンロード
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/82KB]
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(記入例) [PDFファイル/80KB]
熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税の減額措置
2026年3月31日までに建物を一定の熱損失防止(省エネ)改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。
減額対象となる改修工事の要件
- 2008年1月1日以前から所在する専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること。
(貸家の用に供するものは除く) - 次のいずれかの工事で(1)の工事を必ず含むもので、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの。
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)床の断熱性を高める改修工事
(3)天井の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事 ※外気等と接するものの工事に限る - 改修工事費が50万円を超える工事であること。
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。
減額される期間
熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間
申請に必要な書類
- 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士等が発行する省エネ基準に適合する旨の証明書
- 工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
- 改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)
申請書ダウンロード
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/69KB]
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(記入例) [PDFファイル/81KB]
家屋等を新築・増築・取り壊しした場合は届出をお願いします。
家屋等の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。
税務収納課では、市内の新・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは市役所税務収納課に届出をお願いします。
新・増築した場合
住宅、事務所、店舗、倉庫、車庫、物置などの家屋を新・増築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算定するため税務収納課職員が家屋調査にお伺いしますので、完成後お早めにご連絡をお願いします。
※調査時間は、約1時間程度ですので、ご協力をお願いします。
取り壊しをした場合や用途変更した場合
家屋の一部または全部を取り壊した場合や、家屋の用途を変更された場合は、「家屋異動(取り壊し・用途変更)申告書」を提出してください。取り壊した家屋は、申告を受けた翌年度から固定資産税は課税されなくなりますが、申告がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡をお願いします。
※申告書は税務収納課窓口及び各支所窓口にも備え付けております。
申請書ダウンロード
家屋異動(取り壊し・用途変更)申告書 [PDFファイル/32KB]
家屋異動(取り壊し・用途変更)申告書(記入例) [PDFファイル/43KB]
未登記家屋の名義変更をした場合
所有権移転登記を行った家屋は法務局より通知がありますが、未登記の家屋については法務局からの通知がなく、届け出がないと変更の把握が出来ません。そのため、未登記家屋の名義変更(売買等)をされた場合は「家屋補充台帳登録所有者変更申請書」の提出をお願いします。
※申告書は税務収納課窓口及び各支所窓口にも備え付けております。
申請書ダウンロード
家屋課税補充台帳登録所有者変更申請書 [PDFファイル/32KB]
家屋課税補充台帳登録所有者変更申請書(記入例) [PDFファイル/60KB]
家屋調査にご協力をお願いします。
新築・増築等された家屋や取り壊し家屋の随時調査を行っています。対象となる家屋には、建築確認申請が不要な家屋なども含まれます。また、家屋課税台帳と現況の整合性を図るため、建築等をされていなくても随時調査させていただく場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。